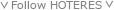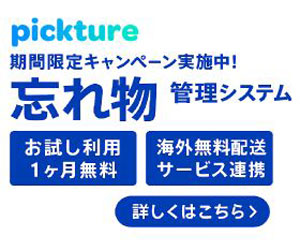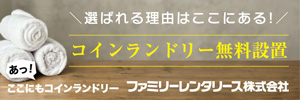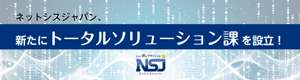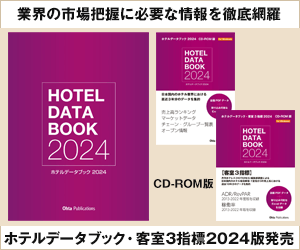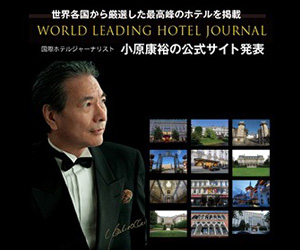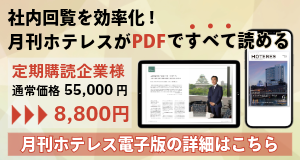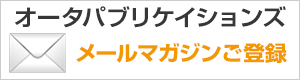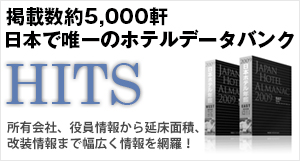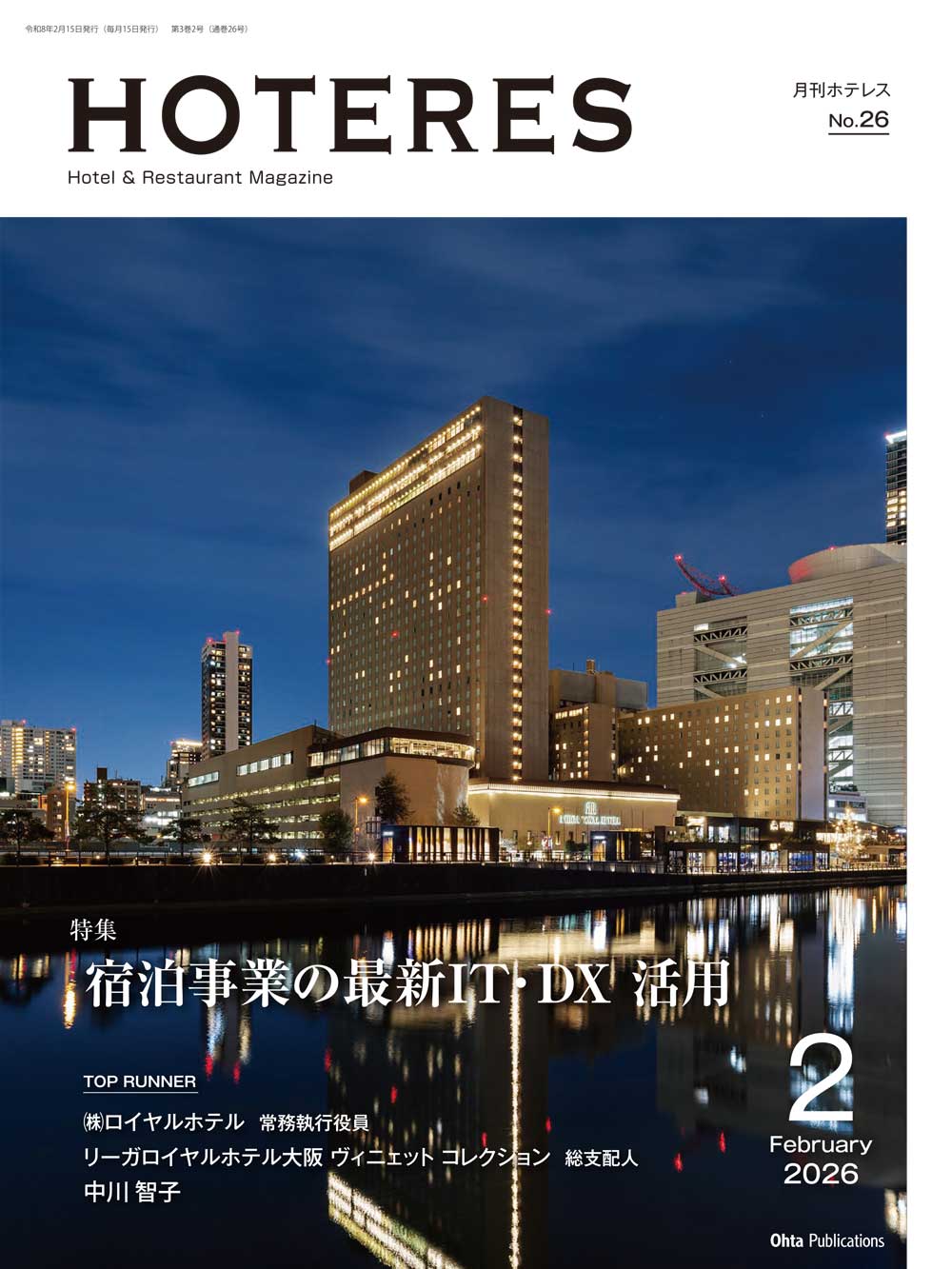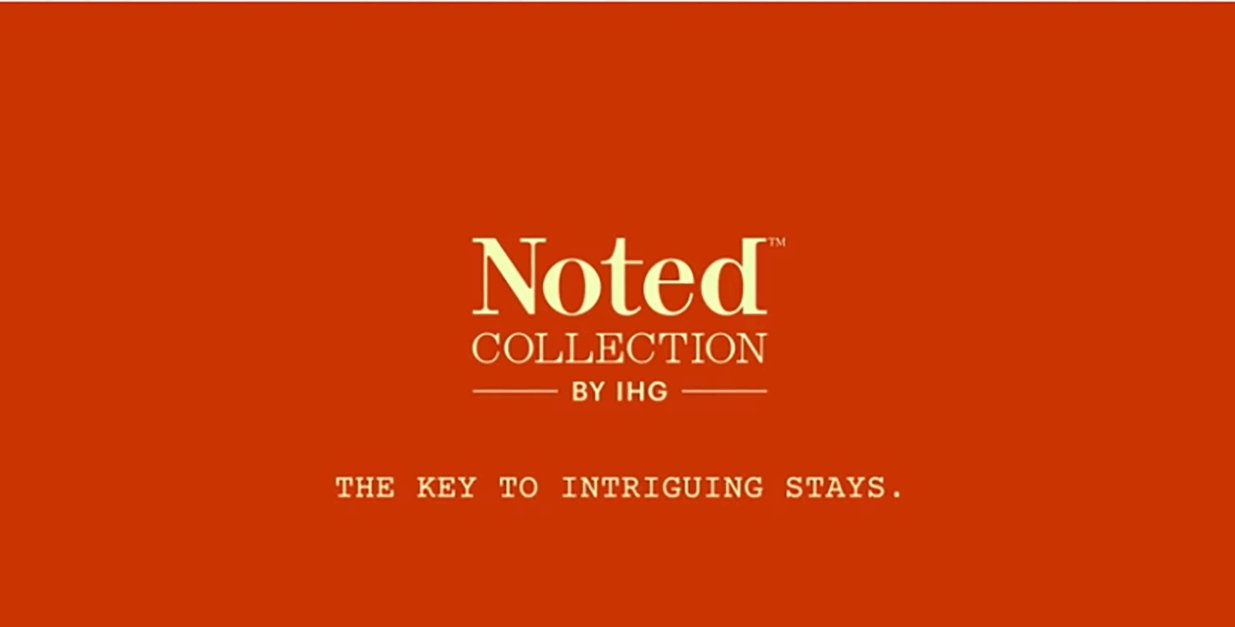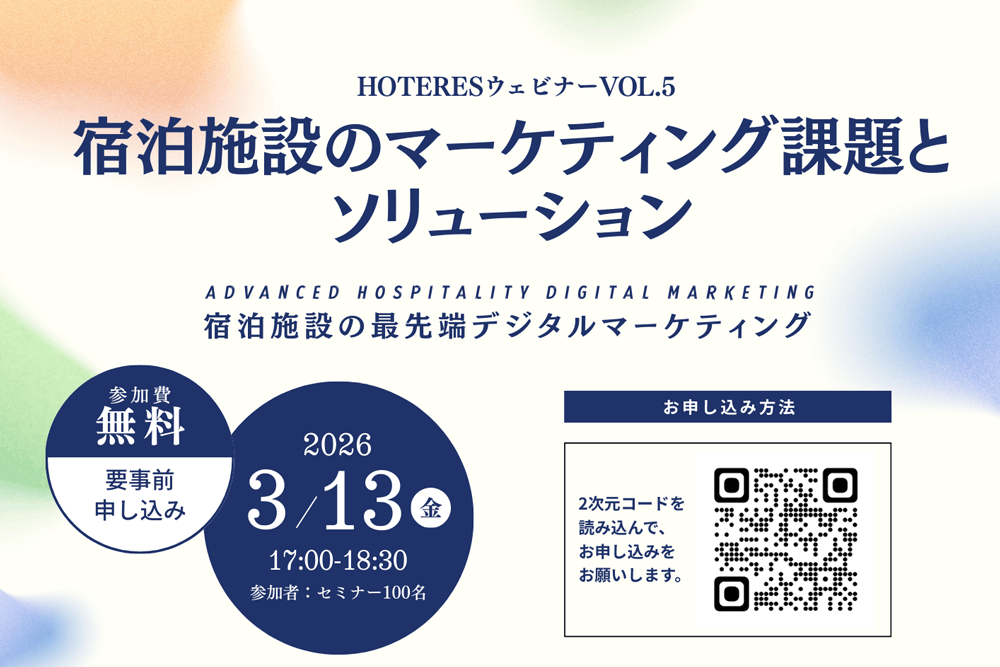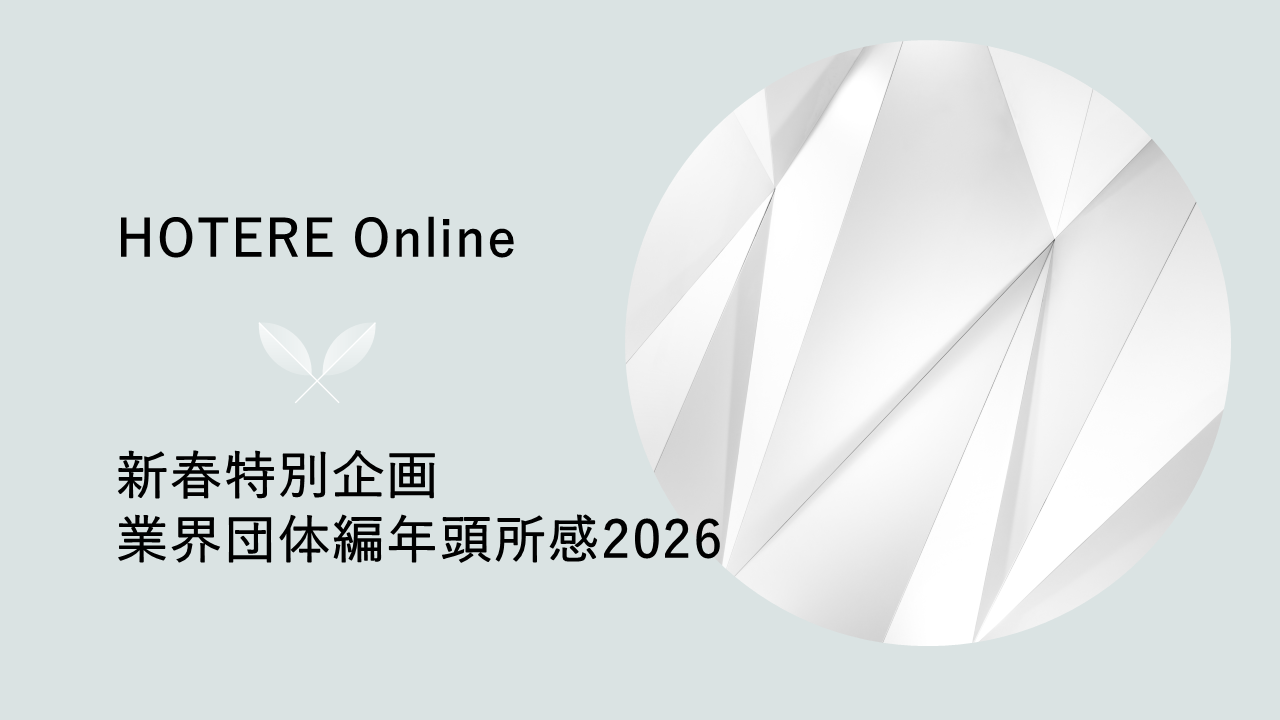HRS&東京B.M.C. 共同開催セミナー レポート
現場を守り、未来を育てる一日 — 2025年9月22日 開催

業界の未来を見据えて
2025年9月22日、HRSと東京B.M.C.の共同開催によるセミナーが行なわれた。冒頭のマイクを握ったのは、(一社)日本ホテル・レストランサービス技能協会(HRS) 会長の森本昌憲氏。「サービスに携わる人材が安心して働ける環境をつくり、次世代につなげていくことが私たちの使命です」と語り、参加者の期待を高めた。
第1部:カスタマーハラスメントという現実
最初のテーマは「カスタマー・ハラスメント」。近年、ホテルやレストランの現場を悩ませる深刻な課題だ。
「東京都条例」の最前線から東京都産業労働局の佐川純也氏は、今年施行された「カスタマーハラスメント防止条例」について解説。悪質なクレーム行為の定義から、企業に求められる相談体制まで、制度の骨格を丁寧に示した。
「従業員を守ることは、企業のブランドを守ることにつながります」
その一言に、多くの参加者がうなずいた。
組織としての覚悟
続いて登壇した奥山敦氏(同協会 企画委員会委員長)は、現場に寄り添った視点で語った。
「一人のスタッフに背負わせてはいけない。トップが旗を振り、法務や外部の専門家と連携する。組織として“守る姿勢”を示すことが何より大事です」
現場を知る言葉は、参加者の心に強く響いた。
第2部:テーブルマナーを問い直す
休憩をはさんで始まったのは、パネルディスカッション「講師として今さら聞けないテーブルマナー」。
ファシリテーターは全国B.M.C会長の菅野俊郎氏。

現場からの声
オークラ東京の阿井希美氏は、若手育成の現場から具体的な課題を提示する。
「知識を覚えるだけでは不十分。お客様の前で“自信を持って振る舞えること”こそが本当のマナー教育です」
一方、テーブルマナー委員会の杉本裕氏は視野を広げる。
「日本独自のホスピタリティをベースにしながらも、国際基準と融合させることが求められています。マナーは文化の橋渡しでもあるのです」
形式を超えて“人を魅了する所作”をどう育てるか。熱を帯びた議論に、会場は真剣に耳を傾けた。
交流から生まれる未来
セミナー終了後の懇親会では、会場の空気が一気に和やかに。
乾杯の挨拶に立った東京B.M.C.会長 永野賢氏は「今日の学びを持ち帰り、互いに磨き合うことで業界全体が強くなる」と呼びかけた。
最後はBIA(ブライダル文化振興協会)の佐々木貴夫氏が中締めを行い、「ここで芽生えたつながりを、ぜひ現場の力に変えてほしい」と結んだ。

守りと挑戦の両輪
今回のセミナーは、前半で「従業員を守る仕組み」、後半で「未来を担う教育」という、業界が直面する二つの課題を真正面から取り上げた。
“守る”と“育てる”——相反するようで実は不可分なテーマを一日で体感できたことに、大きな意味がある。
参加者の多くがメモを取り、質疑応答に積極的に臨む姿は、この業界が変化に本気で向き合っている証拠だった。
セミナーの余韻とともに、現場で働く一人ひとりの背中を支える新しい風が、確かに吹き始めている。
今回のHRS&東京B.M.C.共同セミナーは、単なる知識の習得にとどまらず、現場を支える人材の安心と誇りを守り、未来を育てるための真摯な挑戦だった。
カスタマーハラスメントという重い現実に、法制度と組織的対応の両輪で立ち向かう姿勢。そしてテーブルマナーという伝統的テーマを、若手教育と国際的視野から再定義しようとする試み。そのどれもが「業界全体の底力」を高める投資である。
日本のホテル・レストラン業界は、いま大きな変革期にある。働く人が安心して輝ける環境を築き、次の世代に文化と技術を手渡すことこそが、私たちの使命だ。今回のセミナーは、その道筋を示す一歩として大きな意義を持った。HRS、東京B.M.C.、そして関係各団体の尽力に、編集部を代表して心からの敬意と賛辞を贈りたい。
この取り組みが、業界全体の未来を照らす灯火となることを強く願う。
月刊HOTERES 編集長 義田真平