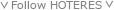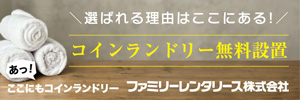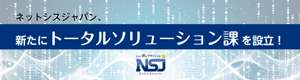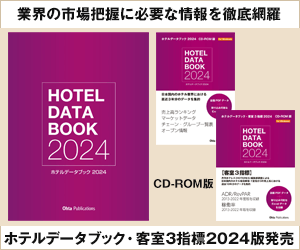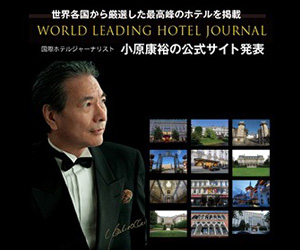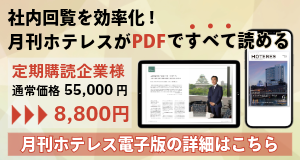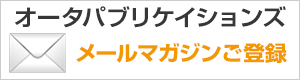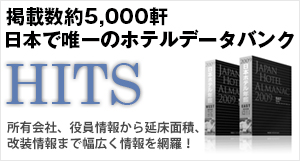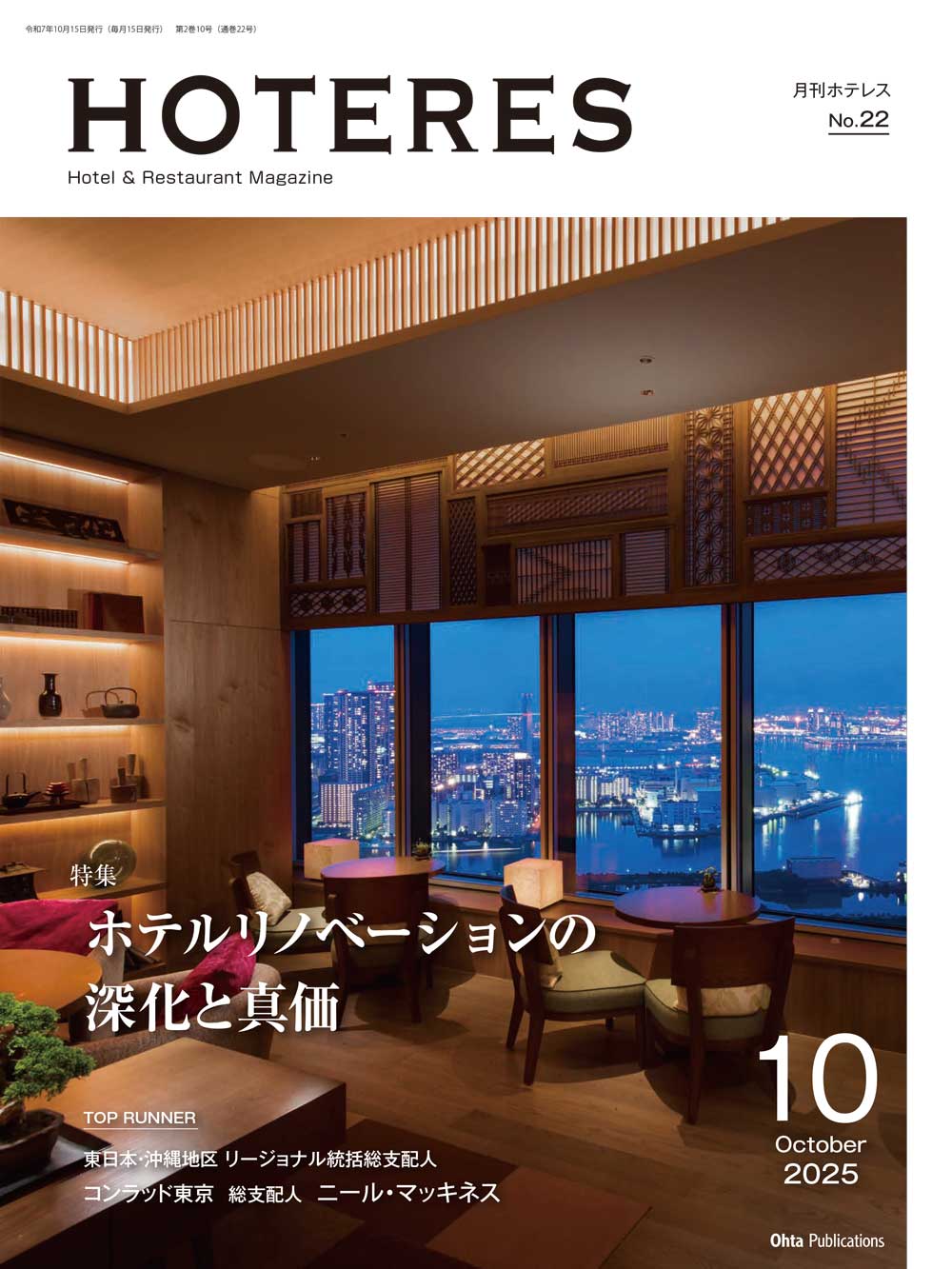2015 年より京都市内にて、えびす旅館という宿泊施設を運営している㈱グローバルネットワーク。翻訳や通訳を主事業とする組織には、パートを含め40 名のスタッフが在籍しており、少人数ながら14 の国籍と13 の言語が混在するという非常にユニークな企業体質を持つ。そんな同社は、今年6 月男性スタッフの希望に応える形で半年間の育児休暇承認を行ない、現在申請に向けた準備を進めている。社会的にも非常に珍しい男性スタッフの長期育児休業承認および申請に伴うお話を、取得者、企業、社会保険労務士それぞれに実情も交えて伺った。




今回、半年間の育児休業承認というお知らせをいただき非常に驚いたのですが、まずは御社について簡単にお聞かせいただけますか。
竹荒 翻訳、通訳サービスを提供する組織として、代表の梶山が設立したのが弊社㈱グローバルネットワークです。設立から10 年が経過し、お客さまの要望に沿って外国語のホームページ制作などを行なっているなかで、特に旅館などからインバウンドに関わる相談が増えるようになりました。そのような外国人集客のコンサルティング業務や実際に宿泊施設の運営業務を請け負って蓄積したノウハウを元に、昨年3 月に小規模ながら「えびす旅館」という施設の自社運営を始めました。現在スタッフはパートを含め40 名、14 の国籍と13 の言語が混在するユニークな組織であり、従業員一人一人の価値観や文化が異なります。その分お互いが支え合おうという意識は強い部分があり、今回国内、特に宿泊業においては珍しい男性スタッフの育児休業承認が実現いたしました。
ではここで取得予定であるアンッティさんからお気持ちと経緯を伺えますか。
アンッティ 私はフィンランドの出身なのですが、自国では私が幼少のころから男性も育児に積極的に参加をしていました。家事の手伝いはもちろん、育児のための休暇取得についてもそうで、文化の一部なんだと思います。そして私自身も、妻の妊娠をきっかけに同じように育児に参加したいと感じ、日本の育児休業について調べ始めました。インターネットを利用し、取得可能期間、休業期間中の収入や負担、その他妻との話し合いを行ない、会社に申し出たのが今年の5 月後半です。
企業としては、最初どのように受けとられましたか。
竹荒 育児休業の取得および申請については国の法律で定められている部分であり、従業員の権利ですが、そういった固いことは抜きにして、雇用側として従業員の成長や家族の理解につながると思い、当初から受け入れる方向で考えていきました。実際の業務や手続きを社労士の松永さんと行なうのは、人事・総務を担当しているニコラになります。また、休業に伴う人材部分での補てんも検討しなければなりませんでしたが、この部分は社内協議の結果、業務引継ぎでの対応ということになりました。
ニコラ 過去に前例のあったことではありませんので、アンッティからの申請と会社の方向性を受け、私自身も実際に取得したという方の話はほぼ耳にしたことがなかったので、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法について改めて調べました。調べてみると取得期間の長さや助成金による国からの企業支援など、色々と整っている部分が多いというのが印象でした。申請までの流れについては松永さんの指示を仰ぎながら、出産前に準備を行なうもの、出産後に行なうものがありますので、確認しながらひとつずつ行なっています。
松永さんにお伺いしたいのですが、日本における育児休暇取得の現状はどのようになっているのでしょうか。
松永 ちょうど先日の7 月26 日、厚生労働省より「平成27 年度雇用均等基本調査」の結果が発表されたところなのですが、女性が81.5%、男性が2.65%、これが最新の育児休業取得率です。昨年から比べると、女性は5.1 ポイントの低下、男性は0.35 ポイントの上昇となっています。男性の取得について、政府目標は2020 年に13%となっていますから、上昇しているといえ、現状かなり遠い位置にあるのは理解いただけると思います。しかも法律で定める育児休業の最長取得が1 年間( ※ 1) にも関わらず、実際の取得期間は8 割以上が1 カ月未満であり、今回のような半年のケースは、2.65%を100 と見た場合のたった0.2%( 表9参照)しかありません。よって育児休業取得の実態は、十分に機能しているかという点ではいささか疑問が残りますし、比較して同社の承認が日本の社会にとってどれほど大きな意味を持っているのかということです。
ニコラ 申請による助成金の利用や、育児休業給付など、個人はもちろん企業としての負担もほとんどありませんし、実務においても総務として特に手間がかかるものではないように感じています。たとえば休業に入る前は、社内に対し育児休業を取得しやすい環境整備を行なうことを義務付けられていますが、厚生労働省発行の告知資料サンプルがあったりしますので、きちんと資料の活用ができれば困ることもありません。
松永 申請に向け、今回同社では就業規則の改定を行なっております。大手企業ではだいたい育児休業における定めの記載があるのですが、中小企業においては今後のことも踏まえどこかのタイミングで規則の再確認を行なうことも必要かもしれません。
育児休業取得率向上に向け、企業が取り組めることはなんなのでしょうか。
松永 大きく向上しない要因の中に、日本人のアイデンティティの部分も関わっていると思いますが、国内企業、特に中小企業においては現在人不足の問題が非常に深刻です。そういった企業にとっては、人材の採用方法を見直し、取得できる状況を作り出すことが最も重要です。休業取得が可能な企業においては、どんどん実績を作っていくのが良いでしょう。社労士という立場からしても、従業員の満足度向上へ積極的に取り組む企業というのは、やりがいを感じるものです。
竹荒 私たちは今回実績を作った側ですので、他の従業員が申し出た場合でも変わらず柔軟に対応していきたいと思います。また育児休業だけでなく、従業員の意思を尊重しつつ、成長につながることは積極的に取り組んでいき、企業価値を高めていきたいと思います。そして事業拡大や新卒採用の折には、女性にも男性にも安心して働いていただける企業であるということを発信していきます。
※ 1 1 年はあくまで育児休業制度における基本であり、保育所に入所できない等の場合、より長い休業が可能。
【企業情報】㈱グローバルネットワーク 所在地= 京都府京都市中京区小川通六角下る元本能寺町382 番地 TEL=075-708-7433 URL=http://www.gncjp.com/