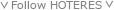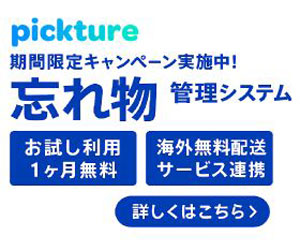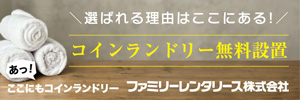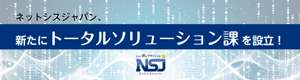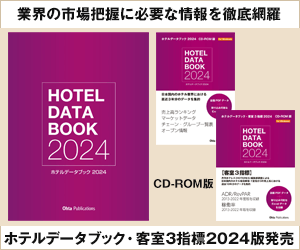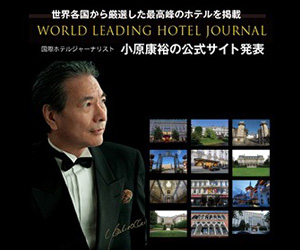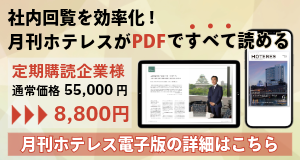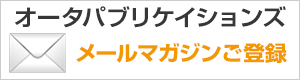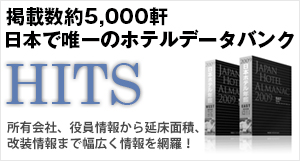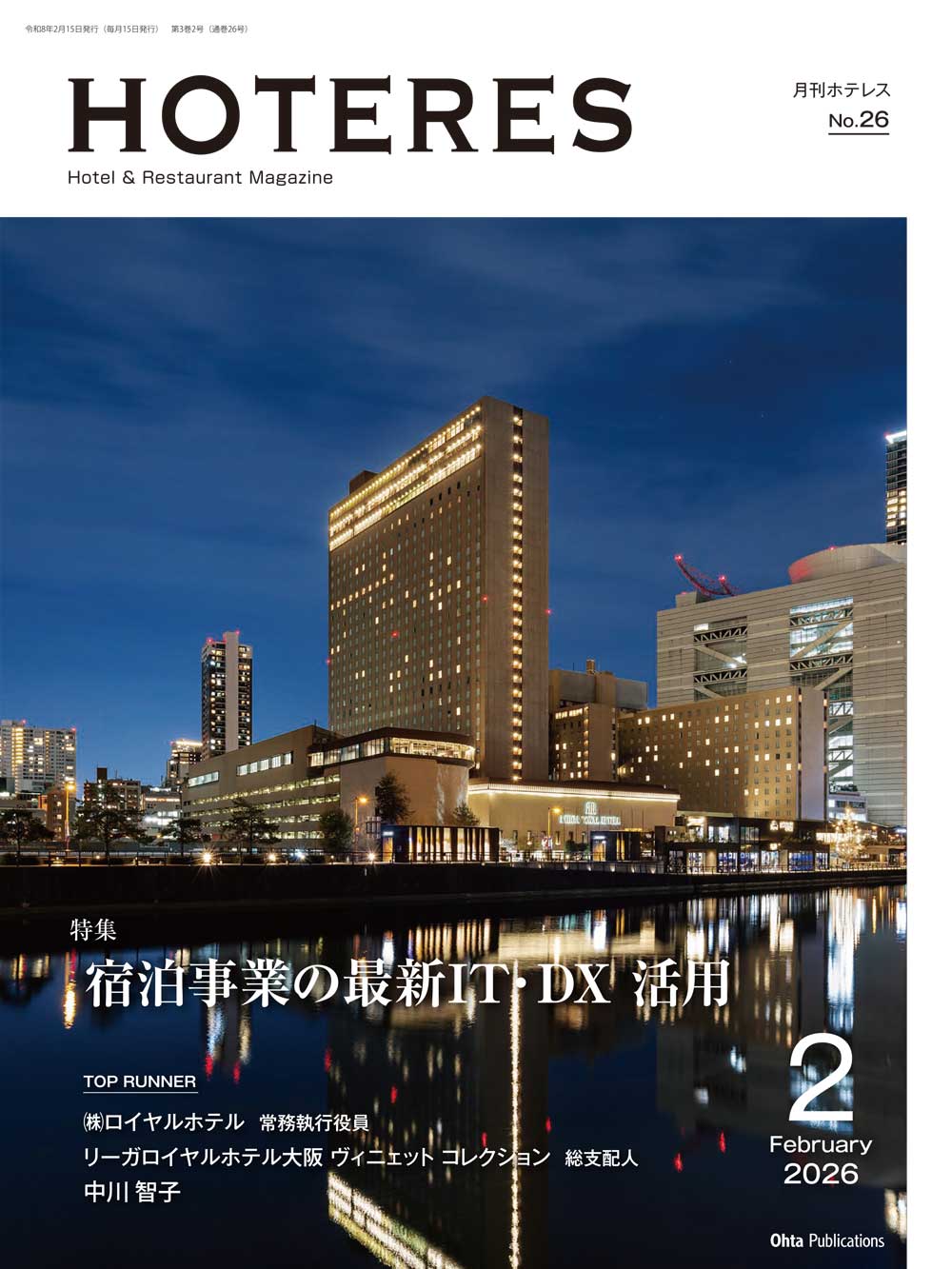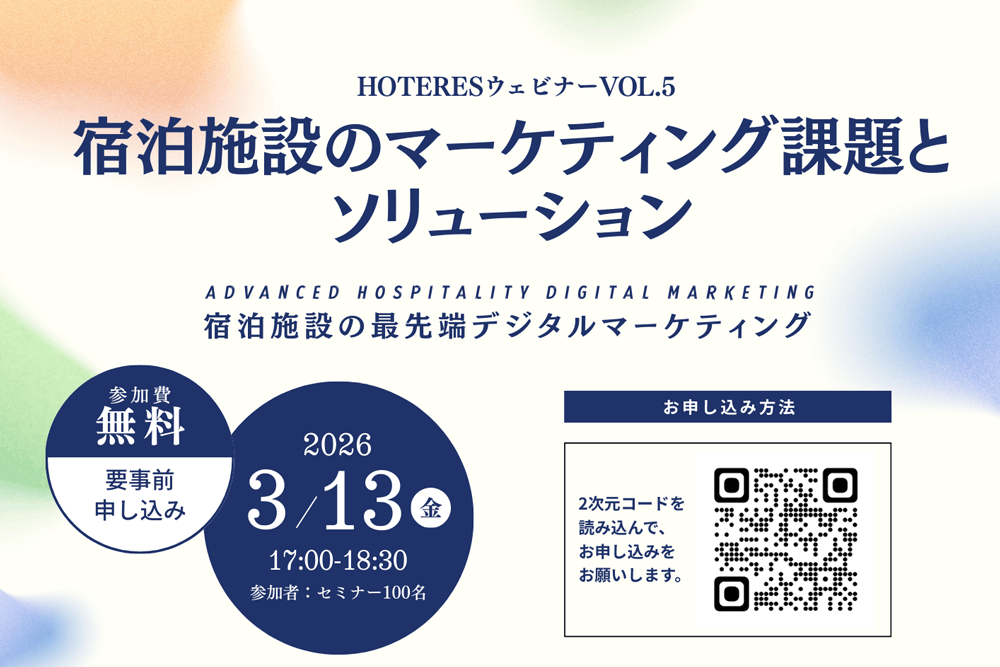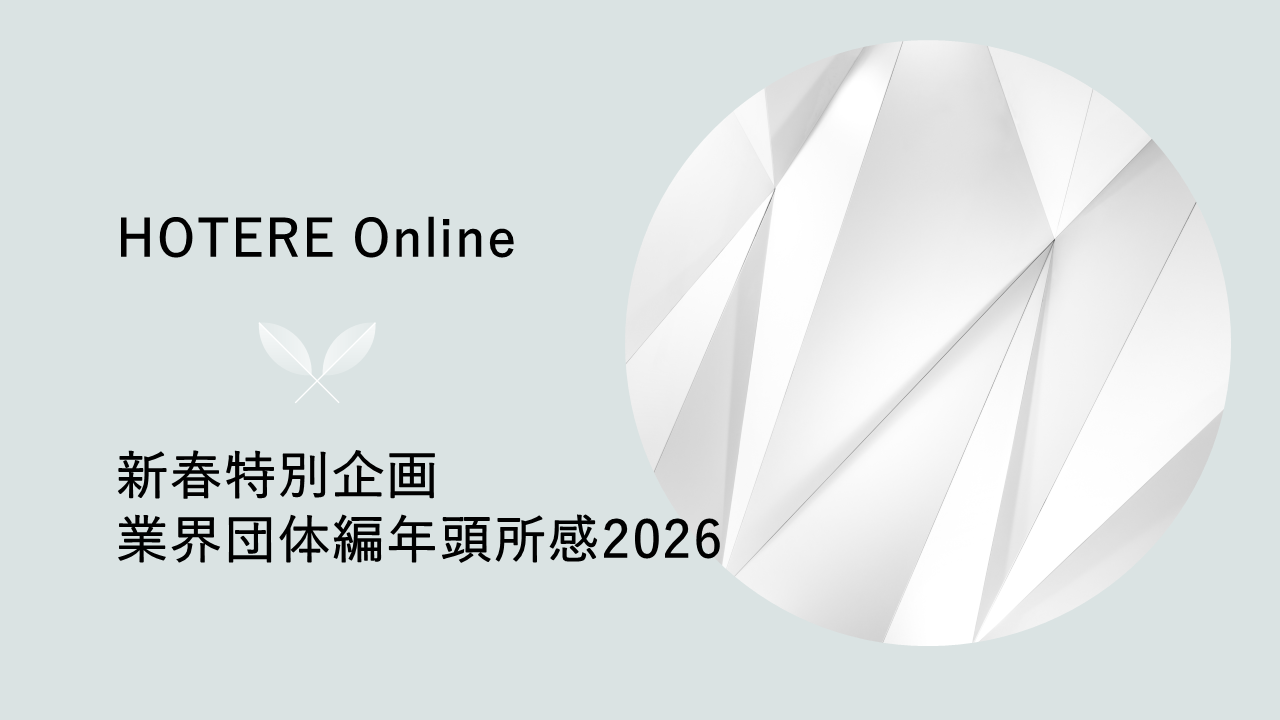Narrative Hospitality Strategyの考え方
では、これを地域観光の中に組み込むためにはどうしたらよいだろうか? 世界的な観光地でもないところが、訪問者を取り込むような物語を作り出すことができるのだろうか?私は、どんなところでも、その場所に応じた物語を作ることができると信じている。では、どのようにしたら魅力的な物語を作り出してゆくことができるのだろうか? あえて挑戦的な提言をするのならば、自分たちが、どれだけすでに存在するその地域の中の物語を自覚し、その中に入り込めるか、と言うことを突き詰めることなのだと私は考える。誰もがある文脈の中で生活しており、それは時に外から見れば滑稽だったりほほえましかったり、あるいはとても魅力的であったりするものだ。それを自覚して演出することができれば、どの町でもおもしろい物語は成り立ちうるものだろう。
その中で、ホテル・旅館業の果たすべき役割は大きい。訪問者がその地域と触れ合う頻度・密度ともに一番高いのがこの業界であると言えるからだ。つまり、この業界は、地域内部の物語を理解しており、それを外からの目で比較的客観的に見つめることもできるという立場にあるのだ。そして、訪問者にとってはその地域への玄関口となるその業界がその物語を演出しなければ、他の所でどれだけそれらしく振舞っても、すべてが嘘くさく感じられ、訪問者は白けた現実世界に戻らざるを得なくなってしまうのだ。
そこで重要になるのは、この業界の人たちが、自分たちがどのようなNarrativeに乗って行動しているのか、と言うことを明確に認識することだろう。現状について多少一方的な見方で分析してみると、ありがちなのは、地域のNarrativeに無頓着で、顧客の要望に応えるのがすべてだ、と言う対応をすることだ。特に、チェーン展開しているようなホテルでは、マニュアルに基づいた対応をして、どこに泊まっても同じ対応をすることがステータスになっているケースもあるかもしれない。もちろん、ビジネスホテルや、プライヴェートリゾートホテルのような場合は、その目的自体がNarrativeなので、そこに干渉しないようになるべく機械的な対応をすることが適切な場合もある。
しかし、その町自体に訪問者が自分でよりどりみどりで好きなものを選べる魅力があるような大都市や、訪問客自身で自由に休日を満喫できるリゾート地のような、圧倒的な競争力を持った観光地などというのは、それほど多く存在するわけではない。その他大勢のあまり個性のなさそうな町は、自分たちがなぜそこに住んでいるのか、と言う魅力をもっと徹底的に突き詰めて、その中でそこに住んでいるわけではない訪問者にでも共感できるような地域のNarrativeを選び出してそれを演出し、たとえビジネス客のような一見のお客さんでも、また戻ってこなくては、と思わせてしまうような仕組みを積極的に作っていく必要があるのだろうと思う。それをせずにマニュアルに基づいた一般的な接客をしていたら、訪問客の心に強い印象を残すことはできず、彼らを再び誘致することなどはまずできないだろう。
つまり、N a r r a t i v eHospitalityとは、一般的にどこのホテル・旅館でも受け入れられるようなサーヴィスだけを提供することではなく、その地域、そのホテル・旅館、そのスタッフでしか演出できないようなNarrativeに基づいて、訪問者の心の中に強烈な印象とともにその経験を記憶させるような接客を心がけることだ。これはもちろん一般的なサーヴィスをないがしろにして、接客側の都合を顧客に押し付けることを意味しているわけではない。むしろ、それに上乗せしてどれだけ顧客の期待を上回るような経験を与えられるか、と言うことを常に意識すべきだ、と言うことを提言するものである。実際問題としては、ディズニーランドのように最初からそのNarrativeに入ることを前提にしてやってきた訪問者ではなく、一般的な旅行者に対していきなりその地域のNarrativeなどといっても、提案する方も受け取る方もなかなか難しいことは言うまでもないことだ。別に一般的な観光案内ならば、そんなことは言われるまでもなく今でもどのホテル・旅館でもやっていることだろう。
問題は、それらの観光情報がどの程度それぞれ有機的につながって訪問者に伝えられているか、と言うことだ。例えば名所がいくつかあったとして、それを単に列挙して伝えているだけでは、たとえそれぞれにある程度の魅力があったとしても、訪問者にはそれほど強い印象となっては届かない。しかしながら、それぞれの名所にどのような接点があるのか、と言うことを関連付けて伝えれば、あまり魅力を感じなかったことでも、がぜん立体的に見えてきて、記憶に残りやすくなる。これは、京都や奈良のような歴史的な町よりも、かえってあまり特色のない地方の方が圧倒的に使いやすい手法だ。京都や奈良は、あまりに歴史が濃すぎて、何を説明しても複雑すぎて頭に入らず、結局、ああすごいね、と言う感じで消化するしかなくなるが、地方の名所というのは、それほど数が多くないがゆえに、どの時代であってもその地域の歴史には必ず刻まれている、と言うことがままある。つまり、ある名所を拠点にしてそこから話をいろいろつないでゆけば、その地域のNarrativeはかなりの程度出来上がってしまうのだ。いったんそうなってしまえば、逆に訪問者の方から、なぜ?といった疑問が出てきて、それに対する反応をしてゆくことによって、訪問者をかなりNarrativeの中に取り込んでしまうことができる。こうした形で訪問客を地域のNarrativeに取り込んでいくような接客をして、リピーターを増やしたり、発信力を高めて新規顧客を呼び込んだりしよう、と言うのがNarrativeHospitality Strategyだ。
具体的運用
では、具体的にどのようにこの戦略を運用していったらよいのだろうか? すでに述べた通り、この戦略では、カギとなるのは役所や観光協会といったところではなく、直接顧客と接する機会の多いホテル・旅館業ということになる。顧客の需要や彼らに受ける情報、または不足していることや顧客の不満を一番知っているのは、顧客に接するホテル・旅館業なのだ。この情報をもとに、ホテル・旅館業は地域を主導してその魅力のブラッシュアップを図っていく必要がある。そのためには、あまりこなれた言い方ではないが、開発(Development)、整備(Arrangement)、伝達(Communication)、受け渡し(Delivery)、反応(Feedback)のサイクルを回していくことが必要だろう。
- 開発
開発は、地域資源の開発だ。開発とはいっても、余裕のあるところならばサグラダ・ファミリアのような新規プロジェクトを始めればよいのだが、ほとんどの所について言えば、それは既存の資源の自分たちによる再発見のプロセスとなるだろう。いくつかの種類の資源について、いくつかの種類のやり方がある。まずは、歴史的な資源について言えば、それらのものがどのような歴史的な意味を持っているのか、と言うことを見つめなおすのが良いのかもしれない。例えば城であればその城がその場所に建てられた理由や、その城主たちにまつわるエピソードなどを集めることによって、いろいろな有機的なつながりが見えてきて、魅力的なNarrativeを作ることができるかもしれない。
ついで、自然の資源について言えば、なるべくわかりやすい比較対象をするのがよさそうだ。専門家にとっては素晴らしい自然の資源であっても、一般の人から見たらよくわからないというものはよくある。そんなときには、事実に即する限りはなるべく大げさな比較をした方が見る人にとってはわかりやすいし、他の人にも伝えやすい。特にそのような比較が見つからないときには、その魅力を一番よく伝えるエピソードや動画・画像というものを活用すべきだろう。どのような形であれ、その魅力を具体化して伝えられるようにすることが重要だ。文化的資源についていえば、無形のものであるが故に、その起源や変移を調べて行く中で、その地域のバックグラウンド的なものが明らかになっていけば、他のものとのつながりもよりはっきりとして、説明がしやすくなるのかもしれない。たとえば、何かのお祭りがあれば、それが始まった社会・経済的な理由があるはずであり、それに関する影響は現在の他の部分にも残っているかもしれない。ある農作物がその地域でよくとれる理由であったり、現在にまでつながるある産業技術分野とのつながりであったりといったことだ。これらの縦糸は、現在のその地域を説明するのにより立体的な彩りを添えるだろう。
- 整備
次に、整備について考察してみる。上の開発で述べたことというのは、おそらく地域アカデミズムのレベルではかなりの部分なされているのだと思う。ただ、それを訪問者に訴えるような魅力的な形に育て上げるには、やはり外部からの客に恒常的に接しているホテル・旅館業界の取り組みが欠かせない。地元アカデミズムの研究は、得てしてひいきの引き倒し的な部分があったり、自分の好きなことを一方的に発信する、といったことになりがちで、外部からの訪問者にとって魅力的な情報になっているか、といわれると、必ずしもそうはなっていないかもしれない。
そこで、より広い視野を持ち、より顧客の反応に敏感なホテル・旅館業界がここに加わり、商品としてより洗練された形にこれらの情報を整備してゆくことが必要になると思うのだ。もちろん、整備の中には、看板やパンフレットといった具体的なものを作る、ということも含まれるが、それよりも重要なのは、実際に自分たちがその説明にどれだけ入り込むことができるのか、という気持ちの部分だ。偉人を輩出した地域では、その偉人を○○さんといった形であたかも友人のように紹介することが自然にできているところもあるが、そういう感じで紹介する本人たちがどこまでその物語に入り込むことができるか、ということなのだ。自分が入り込んでいない話の中に、他の人を巻き込む、などというのは、どう考えても不可能なことだ。
それを念頭に置きつつ、自分が納得するような形、自分がおもしろいと思うような形にNarrativeを作り込んでゆくことが、この整備のパートの重要な部分になってくる。どの地域であっても、そこに現在人が住んでいるということは、何らかの魅力ないしは理由があったから住むようになったはずであり、それを突き詰めれば、必ず他の人の共感を得られる物語は出てくる。なぜなら、人は誰でもどこかに住み、生活しなければならず、それはすべてのひとにとっての共通体験だからだ。自信を持ってそこを練り上げれば、どの地域でも必ず魅力的なNarrativeを作り出すことはできるだろう。
(c)伝達
伝達は、まだそこに訪れていない潜在的顧客に、いかにしてこれらの魅力を伝えるか、ということだ。ここについては、専門家の皆様に対して特に提言できることは多くはないので、それぞれ効率的なやり方を見つけていただければよいと思うのだが、個人的に心がけていることをいくつかメモ代わりに記しておきたい。ランドマーク、地域連携、そしてグローバル発信ということだ。ランドマークは、Narrativeの鍵となる一つのものを中心的にプロモートすることだ。開発の所でも述べたが、ある一つのものを中心にNarrativeを組み立てれば、いろいろのことが関わってくる、ということがある。
だから、いくつかの中途半端な魅力をあれもこれも、という感じで散発的・並列的にプロモートするよりも、ある一つのものを鍵にして、そこから網を広げてゆく形で情報発信するほうが、伝わりやすいのではないか、と個人的には考えている。これは、たとえばこのホテルではあるものを押し、別の旅館で違うものを押す、という形でもよいのではないか、と思う。重要なのは、その地域についてのある一貫した見方を提供する、ということであり、どの見方を選ぶか、ということは訪問者が選べばよいのではないか、と考えるからだ。
こうすれば、次は違う見方で見てみよう、という感じで、地域についてのリピーターは増えるかもしれない。地域連携についていえば、近隣地域との連携という手法もあるのだろうが、ここで提案したいのは、Narrativeを部分的に共有するような遠隔地域との連携だ。たとえば同じ大名にゆかりのある地域であったり、同じ産業を共有している地域であったり、そのほかの何らかの特徴を共有している地域と連携するのは、近隣連携よりも競争的ではなく、より協調的な関係を築くことができそうだ。そしてそれは、近隣連携よりも外部者の視点を提供してくれるものであり、より視野が広がるだろう。グローバル発信についていえば、たとえ日本国内ではそれほど特徴的ではないと思われることでも、日本についての情報がそれほどない外国に対して最初に、そして最も魅力的に情報発信をすれば、海外においてはその地域がその特徴の代名詞のように印象づけられるかもしれず、非常に効果は高いだろう。
(d)受け渡し
受け渡しは、実際に訪問された方々をどのようにお迎えするか、ということになる。ここも、ホテル・旅館業の専門分野なので、特に私が付け加えることもないだろう。ただ、意識すべきことは、スタンダードとローカルのサーヴィスを両立し、自然な形でNarrativeに誘導することだ。ホテル・旅館業の対応については、実務に関わったことのない私が提言するのはおこがましいので、それ以外の部分でいくつかのことを取り上げておきたい。自然さ、体験、発信しやすさだ。
自然さというのは、宿で聞いたNarrativeが外での反応と齟齬が起きないように注意することだ。これは、ホテル・旅館業だけに言ってもどうにもならないことだが、情報発信の方向性があまりに外向きになりすぎるが故に、現地の人の認識とかけ離れてしまい、実際に観光すると全くNarrativeに入り込めずにかえってがっかりさせてしまうことのないようにしたい、ということだ。これを防ぐためには、Narrativeの内容については常に現地の人々とすりあわせる一方で、現地に少なくとも一人のその内容をしっかり理解した人を確保し、他の人が聞かれたときには『私はわからないが○○さんに聞けばわかるのでは。』という流し方ができるようにすることも重要になるかもしれない。いずれにせよ、せっかく作り上げた世界観を、現実が破壊してしまわないように注意することは重要になってくるだろう。体験というのは、来たお客さんに対しては、なるべく何かを体験できる形で提供するのがいいのでは、ということだ。ただ見て回るよりも、実際に何かをした、という体験の方が、確実に記憶に残るだろう。その印象は、リピートにもつながりうるし、口コミにもつながりうる。同じ時間を過ごさせるのならば、できるだけ印象深くその時間を記憶に刻みつけたいものである。発信しやすさというのは、前の体験にもつながることだが、訪問者がその経験をなるべく発信しやすい形にしてサーヴィスを提供する、ということだ。
言うまでもないことだが、今の時代はインターネットが広く行き渡って、そこでの口コミが大変重要になっている。その中で、エピソードなり、体験なりが他の人に話したい、ということであれば、それはSNSなどでどんどん拡散し、無料の宣伝効果が現れる。だから、なるべくキャッチーなNarrativeの方が伝えやすいし、印象的な体験の方が発信してもらいやすいと私は考えるのだ。結局の所、自分が入り込みやすい話は一般的には他の人も入り込みやすいはずだ、と思い、なるべく自分が感情移入できるようなNarrativeを作り、それと同時に記憶に残るような体験を提供し、その画像や映像を魅力的に映して顧客に渡して情報発信してもらいやすくする、といったような取り組みを継続的にしてゆくのがよいのだろう。一方で、誰もがコンピューターを扱えるわけでもないので、撮った画像をすぐに絵はがきにできるような仕組みを作るのも必要になるかもしれない。インターネットの情報は陳腐化しやすく、アナログの絵葉書のようなものの方がむしろ長く送り先に置いておかれるかもしれない。いろんな側面から情報発信しやすい形を整えることは、その努力の分だけ報われる地道な営業戦略ではないだろうか。
(e)反応
反応は、訪問顧客の感想や意見などをしっかりと集め、それをさらなる開発や整備に反映させることだ。地域観光において、これは大きく欠けている点かと思われる。なぜなら、観光協会や観光案内は、基本的に無料サーヴィスであるが故に、顧客側の要求水準もそれほど高くなく、よって返ってくるフィードバックにもそれほどの密度は期待できない。しかしながら、有料サーヴィスのホテルや旅館業がより前面に立って地域観光に取り組めば、その要求水準はより高くなり、故に返ってくるフィードバックもより実際的で本音に近いものが出てくるだろう。そこで得られる情報は、さらなる改善のための重要なツールとなるだろう。この一点を取ってしても、ホテル・旅館業がこのNarrativeHospitality Strategyを推進する大きな意味があるといえる。
(f)D-A-C-D-Fサイクル
この、D-A-C-D-Fサイクルを回すことによって、より顧客の心をつかむNarrativeを練り上げ、既存顧客のリピーター化とそこからの情報発信による新規顧客の開拓という二つの目標をなるべく効率的に成し遂げようというのが、N a r r a t i v eHospitality Strategyのポイントである。繰り返しになるが、顧客が入り込みやすく、また口に出して他の人に話したくなるようなNarrativeを構築し、その世界観をなるべく忠実に再現して顧客に提供することが、この戦略の肝である。
ホテル・旅館業の役割
では、最後に、その中におけるホテル・旅館業の役割をもう一度整理してみたい。その役割は、大きく3つに分類される。顧客の望む物語と地域の提供できる物語の情報を集めそのマッチングを行う役割、そのマッチングの結果としてのどちらもが納得でき入り込めるNarrativeを構築する役割、そしてそのNarrativeの舞台背景整備や役作りを主導する役割だ。これはいずれも訪問顧客の状況をよく理解している立場の人たちがやらなければ、とても中途半端な、何のためにやっているのかよくわからない自己満足的なことになってしまうので、外部者の視点をしっかりと保つことのできるホテル・旅館業が主導するのが最適であると思われるものばかりだ。マッチングの部分では、顧客の要求や望みを集めるのは、直接顧客に接するホテル・旅館業であり、その情報はなるべくゆがみのない形で実現するのが望ましいことは言うまでもない。
であるならば、顧客からの直接情報を集めた者自身が供給できる情報とのマッチングを図っていくのが一番歪みの少ない形になるだろう。Narrativeの構築についても、その基本構造は受け手と出してのコミュニケーションであり、その中で伝言ゲームの悪い癖が出ないようにするためには、なるべく情報加工は1か所で行い、ゆがみを少なくするのが望ましい。その点で、情報ハブたるホテル・旅館業が中心となってNarrativeを仕上げてゆくのが一番効率的であると言える。背景整備や役作りについて言えば、最初から芝居や演劇をやるとわかっている場であるならば演出家は別にいた方が魅力的になるかもしれないが、地域においてその芝居をやることについて必ずしもコンセンサスがあるわけではない場合においては、物語を作った人自身が演出まで行わなければどこかで必ずずれてきてしまうだろう。必ずしもすべてを自分でやるという必要はないが、少なくともスーパーヴァイザー的な立場で演出についての主導権は持っておいた方が、これらの増えた業務に対して、どのようにビジネスモデルを立てていくのか、と言うことも大きな問題になるが、最も望ましいのは、この戦略をとることによって顧客ベースが広がり、本業が順調に進むことによって費用を回収してゆくことだ。
一番の受益者がホテル・旅館業になることを考えれば、こうした形で費用を内部化することが、一番地域の理解を得られそうな気がする。それをする余裕がないときには、地域や公的機関を巻き込んで別の形で収益モデルを組み立てることが必要となる。しかし、この形では、基本的にタコの足を自分で食べていることになり、はっきり言ってしまえばこの戦略をとること自体が疑問にさらされてしまいかねない。そのあたりをよく考慮したうえで、それぞれが適切なビジネスモデルを構築することが望まれる。
結語
以上、ホテル・旅館業の新たな戦略の視座として、N a r r a t i v eHospitality Strategyについて考察してみた。この提案を通して、ホテル・旅館業において、何らかの形で視野が広がり、地域との協力関係が進み、更にそれが利益にまでつながることになれば、望外の喜びである。

尾嵜悌之
Ozaki Tomoyuki
ロールキャベツ仕掛人
【プロフィール】
大学卒業後、商社勤務を経て青年海外協力隊に参加。そこで地域開発の魅力に目覚め、アイルランドでビジネスを学び、その帰路に陸路で様々な都市を見て回り、それを参考に地元東三河地域の開発に取り組んでいる。現在は、ロールキャベツを中心に町おこしに取り組む。飲食店になるべく地元産のキャベツを使ってロールキャベツを作って頂き、それをまとめて広報をすることによって特産品に育ててゆく取り組みを行っている。観光という側面では、英語版のサイトを作り、観光情報を発信。平成22年に内閣府の社会企業インキュベーション事業に第1期で選定され、新聞2紙に掲載されている。