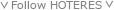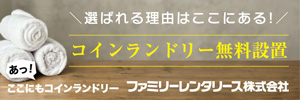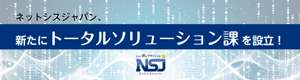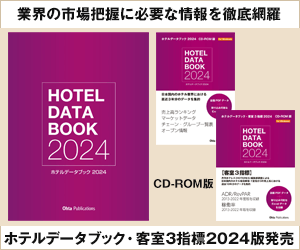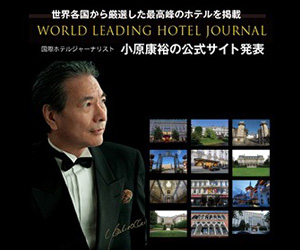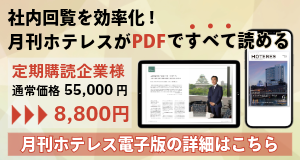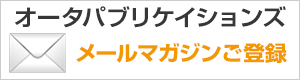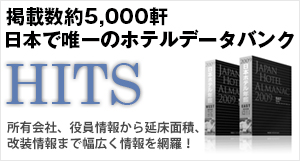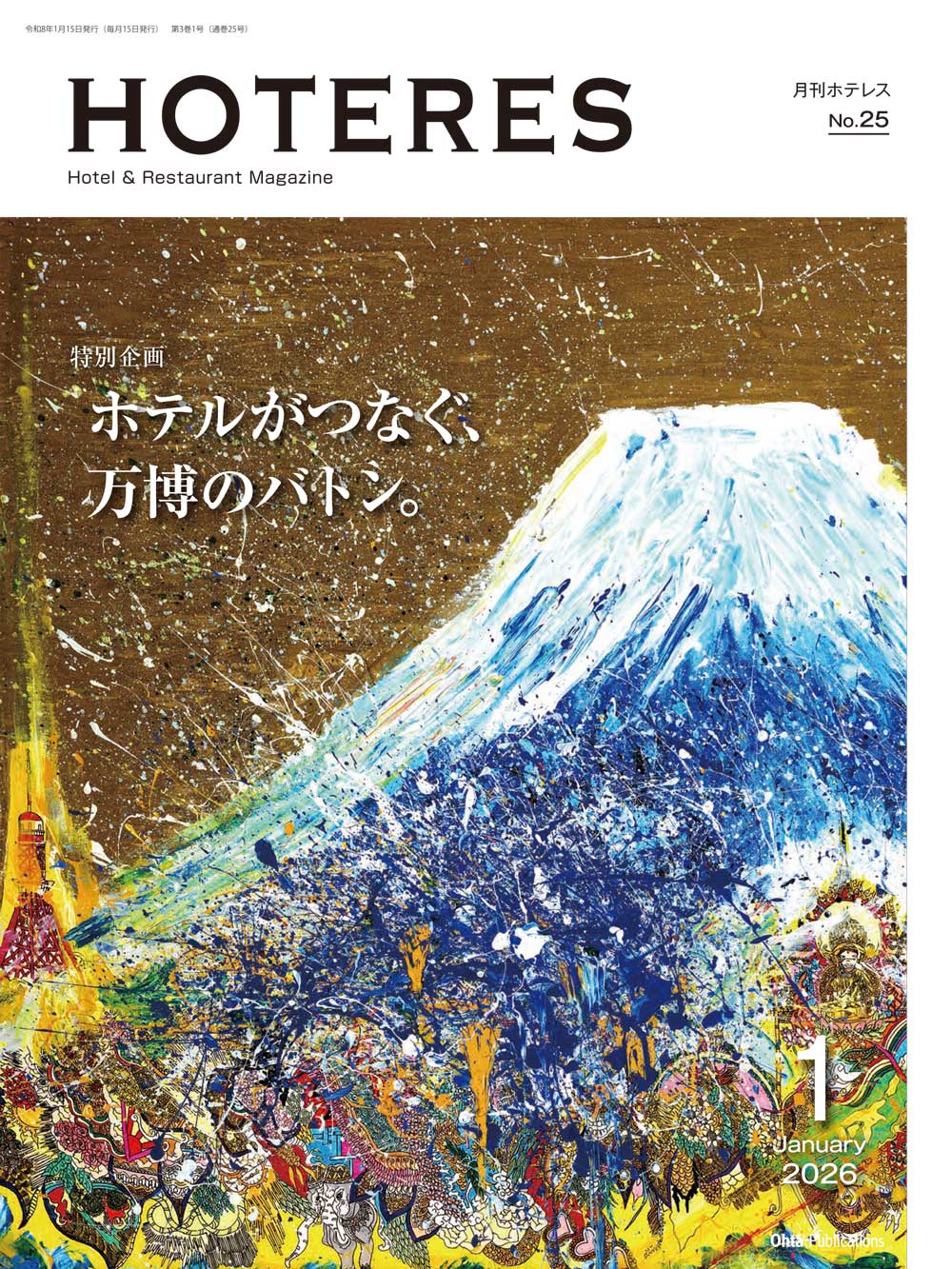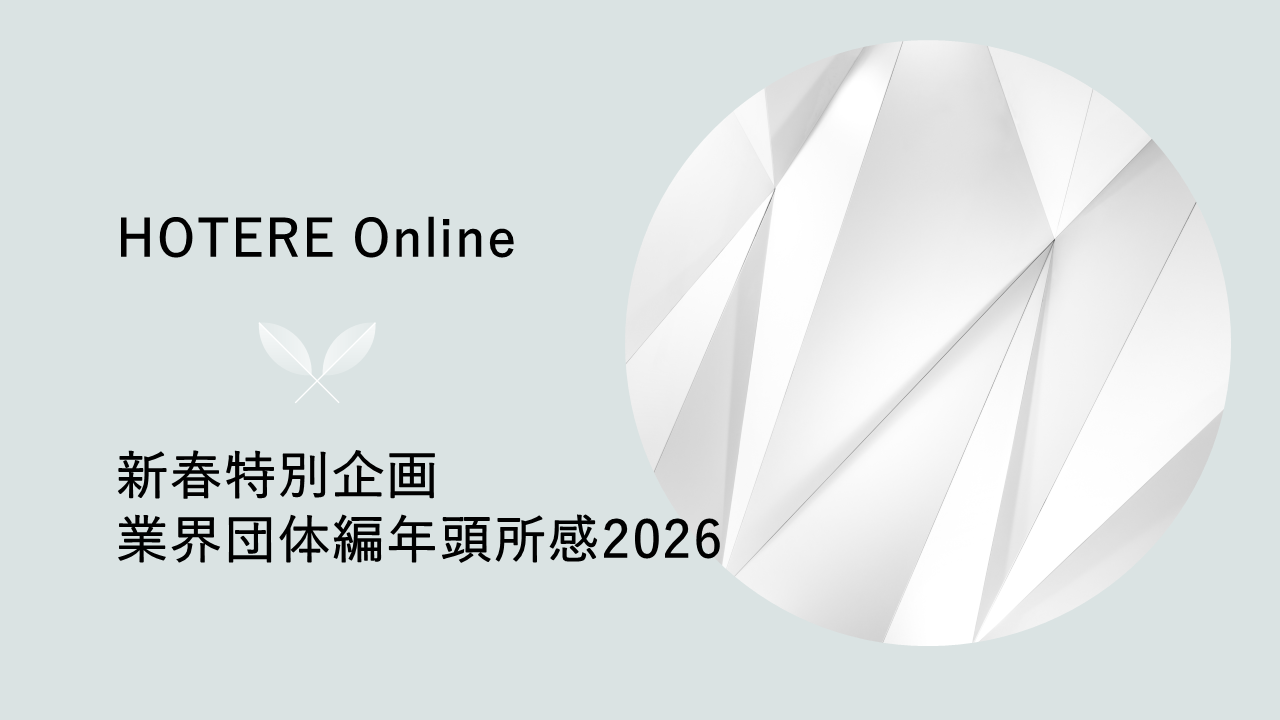1954年。開業から2年の折に10,500匹の蛍が寄贈され、庭園で観賞したことから始まった‟ほたる観賞の夕べ“。「東京の子どもに蛍を見せたい」「上京してきた若者たちに蛍舞う原風景に故郷を感じてほしい」という創業者の思いからはじまり、今日では「ホテル椿山荘東京」の初夏の風物詩として多くのお客さまから愛される行事になっている
今年も「ホテル椿山荘東京(以下、「椿山荘」)」の庭園を舞台に、‟ほたるの夕べ“が開催されている。加えて、今年は三重塔の‟圓通閣(えんつうかく)”が東広島の篁山竹林寺から移築されて100周年にあたる。それを記念し、三重塔前の芝生エリアや塔を囲むように霧が出現する庭園演出、‟天空の三重塔(パゴダ)“も開催され、例年よりも更に幻想的な雰囲気の中で蛍観賞を楽しめる空間になっており、連日大勢のお客さまが訪れている。昨今では、日本の伝統的な夏の歳時記を体験したいと望む、インバウンド観光客の訪問も増えている。
ちなみに同庭園では、蛍だけでなく、椿や桜、新緑、涼夏、秋、冬といった季節ごとの風景も大切にしており、これらを‟ホテル椿山荘東京の七季“と呼び、季節の移ろいを一年を通じて味わえるよう、様々な工夫が凝らされている。
これらの取り組みは、単に景観を整えることを目的とするのではなく、蛍をはじめとする庭園内の生きものが自然のリズムの中で共生できる環境を保つことにも重きを置いている。特に蛍は、きれいな水辺と豊かな植生がなければ生息できない繊細な生きものであるため、庭園では水質の管理や照明の照度調節、在来植物の保全など、様々な工夫と配慮が施されている。中でも、蛍の幼虫が地上に上陸する3月末までに剪定作業を終えるなど、細やかな配慮が徹底されており、自然と共に生きる庭園としての姿勢が随所に表れている。なお、これら庭園の維持・管理にあたっては、‟庭園支配人“という、庭園運営に特化した専任の支配人が配置されており、同社が庭園保全に対して真摯に取り組んでいる姿勢がうかがえる。さらに同社の企業努力は社会的にも大きく評価されており、‟日本空間デザイン賞 銀賞”、”Prix Villergiature Awards グランプリ“、"iF DESIGN AWARD”を受賞している他、”日本夜景遺産“にも登録されている。

‟ほたるの夕べ“開催中は、館内のさまざまなレストランやイベントで蛍をテーマにした料理が提供される。‟ディナービュッフェ”。メニューには、東広島の名物料理‟美酒鍋“や広島県の八朔で作られたリキュールを使用した‟蛍の光”など、三重塔にちなんだものや、お子さまむけにホテル椿山荘東京オリジナルキャラクターのほたる支配人が刻印されたハンバーガーなどもある
さらに今回注目したいのが、これらSDGsの取り組みが地域貢献やおもてなしにエレガントに繋げられている点だ。
例えば、蛍の飼育については2003年からは、コロナ禍の21年を除き、地元地域の小学生を招待し、‟ほたるの幼虫放流式“を毎年開催している。もちろん、これらの蛍が成虫となり、美しい光を放つ時期には彼らを再度招待し、その姿を観賞する機会も提供している。また、24年からは新たなSDGsの取り組みとして養蜂箱をバンケット棟プラザの屋上に設置し、養蜂を新たに始めた。基本的にミツバチたちは庭園内に生息する植物から採蜜しているといい(※一部、施設外からも採密していると予想される)、庭園内の自然環境および生物多様性保全に対する取り組みをより強化した形だ。ちなみに日々の養蜂作業は養蜂家と協力し、さらに巣房から抽出後のハチミツは地域の障害者の就業支援活動のひとつとして文京区の障害者支援施設「リアン文京」「JSPちよだ」に瓶詰とラベル貼付を委託している。それらを同社が購入し、ホテルオリジナルハチミツ‟GARDEN HONEY”として販売している。同社では養蜂の取り組みについても今後、強化していくといい、さらに今夏は自由研究サポートプランとしても商品化し、ミツバチの生態の学習や遠心分離機を使った採蜜体験ができる‟ミツバチ博士になろう!夏の自由研究ステイ“も販売する。これらのプランは子供たちの情操教育に良いだけでなく、地域社会とのつながりや環境保全への意識を育む貴重な機会の提供になっている。さらに、これらの記憶が将来的に再訪動機となり、世代を超えて施設と持続可能な関係性を築いていく未来すら感じられる。
昨今、企業としてサステナビリティやSDGsへの積極的な取り組みが強く求められる中、単なる一過性の企画や表面的な施策で終わってしまっているケースも散見される。“持続する”ということが、いかに難しいかだ。その中にあって、同社の‟蛍の飼育“のように半世紀を超えて継続されている取り組みは、まさに本物であり、また観賞会や放流体験のようにエンターテインメント化したコンテンツとしてお客さまの感動や喜びにつながる企画を創生している点も素晴らしい。これらは単なるCSRにとどまらず、地域や社会と真正面から向き合う姿勢であり、深い納得と信頼を生み出している。もちろん、50年以上にも及ぶ取り組みである。一朝一夕に真似できるものではないが、宿泊事業者がSDGsの取り組みとお客様満足度の両立を可能とする取り組みを手掛ける際、同社の変革を参考にすることは非常に有益である。
ぜひ、「椿山荘」が各季節に庭園で展開するさまざまな企画に足を運んでみてもらいたい。
「ホテル椿山荘東京」
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/








担当:毛利愼 ✉mohri@ohtapub.co.jp